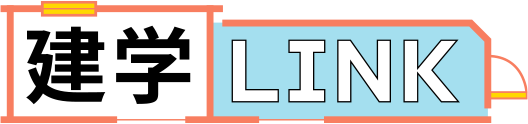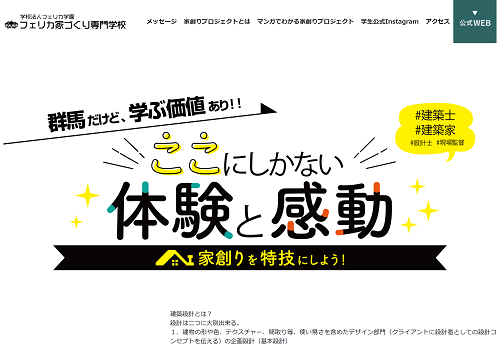独学で建築士になるためには?
建築士はデザインだけではなく、法律や防災といった面も考慮して家やビルの設計図を作る重要な仕事です。そのやりがいや社会貢献性の高さから、近年建築士の資格を取りたいという方も増えてきています。中には独学で、建築士の資格取得を目指そうと考えている方もいるでしょう。
しかし、同時に本当に建築士は独学で合格できるのか、どのように勉強を進めていけばいいのかといった悩みを持つ方もいるはずです。そこで今回は 建築士を独学で取得するための方法や合格するために必要なものなどをお伝えします。
建築士は独学で合格できるのか否か
結論、建築士は独学で合格できます。一級・二級でも、独学で合格されている方は多くいらっしゃいます。
というのも、日本の建築士の合格基準は「上位何番目までは合格」というものではなく、一定の合格基準を定めているからです。
つまり、現時点での知識や経験は問わず、これからどれだけ勉強をして・合格基準に達するかがポイントとなります。もちろん、建築業界での実務・建築を学んだ経験などがあれば、少なからず有利になるのは間違いありません。
ただ、独学での合格は「可能」というだけで、建築士は決して簡単な資格試験ではないのも事実です。
公益財団法人建築技術教育普及センターの情報によると、令和5年度の二級建築士の総合合格率は22.3%(※1)、一級建築士は9.9%(※2)でした。 試験は製図と学科に分かれており、それぞれの合格率はもう少し高いのですが、総合合格率となると一気に数値が下がります。
必要な勉強時間
建築士に合格するために必要な勉強時間についてですが、それぞれ分けてお伝えします。
一級建築士と二級建築士の難易度は異なり、必要な勉強時間の多さも差があるためです。
一級建築士
一級建築士に独学で合格するために必要な勉強時間は、一般的に1,000時間以上だと言われています。初学者であれば2,000時間以上かかることも珍しくありません。
これは中小企業診断士や行政書士と同等で、難易度が高く資格の取得まで数年かかる方も多くなります。
もし1年間で一級建築士に合格すると考えると、初学者の方であれば1日あたり5時間以上の勉強が必要となるでしょう。
二級建築士
二級建築士の場合は初学者の方で1,000時間、建築系に知見のある方であれば500時間程度を目安にするとよいでしょう。一日1.5~3時間程の勉強が必要な計算です。
一級建築士よりは合格までのハードルが低いと言えそうですが、やはり合格までの道のりは大変なのは間違いないでしょう。
合格するための必要な勉強時間はあくまでも目安であり、この通りに勉強したからといって必ず合格するわけではありません。1日3時間勉強するのであれば、その分集中する必要があります。
また、分からない専門用語や言い回しを調べる時間も必要です。
限られた時間で、なるべく合格に近づけるような勉強方法も模索していくことになります。
建築士になるための勉強方法
建築士の試験は大きく分けて学科試験と製図試験の2つがあります。
学科試験
学科試験の勉強方法はテキストから過去問への移行です。資格試験の学科試験対策の勉強は、テキストを2~3回ほど通読して過去問に入る方法があります。
これは建築士に限らず、学科試験対策の鉄則です。
テキストの通読
テキスト通読の際に一字一句全てを理解する必要はありません。完璧である必要はなく、ある程度「ご自身の言葉」で内容を説明できるような理解度を目指しましょう。
もちろん、テキストの全てを理解できればベストですが、最初の段階ではそこまでできなくても大丈夫です。
過去問
テキストの理解ができたら、過去問に入ります。過去5年分ほどを用意しておけば大丈夫です。
そして、現段階で理解できていることをベースに問題を解いていきます。初回に過去問を解いた段階では、大体全体の2~3割が正解できれば十分です。
ただ、それでは合格ラインに達しないので、できなかった部分はテキストを見ながら理解していきましょう。
加えて、忘れずに行っていきたいのが出題傾向(範囲や求められる知識の深さ)の分析です。
資格試験というものは、出題にある程度の傾向があります。二級建築士の場合、「建築計画・建築構造・建築施工」の出題傾向は大きく変わりません。このような「多く出題されやすいお題」を押さえておくことが合格への1歩となります。
もちろん、過去問にはなかった新傾向の問題が出題されるケースもあります。ただ、過去の傾向がある以上、新傾向の問題が大部分を締めることは考えづらいものです。新傾向の問題が出題されてもそれ以外で得点を重ねれば合格ラインには達します。
まずは出題傾向がある問題を、確実に正解できるレベルにまで持っていきましょう。それ以外は「知っている」レベルを目指しておきます。
問題集
過去問の分析を行い、重点的に勉強するポイントがわかったら問題集をこなすとより合格が見えてきます。
ここで注意していただきたいのは「問題集は1冊だけ」という点です。
いくつか問題集を買い込んで「それをひたすら解く」方もいらっしゃいますが、必ずしもそれが効果的というわけではありません。決めた1冊を2~3周した方が身になる場合もあります。何周か繰り返していけば、問題とその解説文を覚えてしまうぐらいになるでしょう。
その段階で過去問を解いてみると、合格ラインに達することも多くなるはずです。
法規
学科試験の中には「法規」という科目があります。建築基準法が掲載された法規集で、正誤を調べる問題です。そのため、法規集からいかに早く正解を探し出せるかがポイントになります。言い換えれば、法規集の使い方に慣れていなければいけません。
そのため、早い段階で法規の勉強に入るようにしましょう。法規の勉強についても過去問をベースに行い、選択肢のひっかけや「法規集のどこに正解があるか」をわかるようにトレーニングしておくのがおすすめです。演習を繰り返すに連れて問題の理解度が高くなり、法規集を引くスピードも上がります。
製図試験
製図試験は学科試験とは性質が異なる内容です。課題の内容理解と設計条件をもとに図面の計画をまとめるプランニングが求められます。
対策としては、まず模範解答を複写して製図の書き方に慣れることです。さらに製図を書くにはプランニングがまとまっている必要があるため、そのスピードが合格のカギとなります。
ただ、製図は過去に勉強した方以外にとって複雑に感じるかもしれません。
その場合は、通信講座を受講するのも一つの方法です。
実際に、学科は独学・製図は通信講座で学ぶ方もいます。通信講座を受講すればプランニングのまとめ方から課題内容の解説も受けられるのがメリットです。加えて、模擬テストや講師による添削が受けられます。
睡眠時間も勉強時間と思うべき!
睡眠によって記憶が定着する
独学で建築士を目指す人の中には、睡眠時間を削って勉強時間に充てようとする人も少なくありません。
しかし、勉強のために睡眠時間を削ったり徹夜を続けたりすることは、結果的に勉強の効率を低下させるため原則的にNGです。
そもそも人間の脳は睡眠中に記憶の整理や疲労回復をするとされており、むしろしっかりと眠ることで学んだ内容が記憶として脳に定着し、改めて勉強を進めた際に理解が深まることもあるでしょう。
また、睡眠不足が続いて体調を崩してしまえば、勉強のスケジュールが狂ったり生活に悪影響を及ぼしたりと、デメリットが増大します。
そのため、きちんと休息する時間や睡眠時間も、勉強時間の一部として考えておくことが重要です。
睡眠の質を高めることが重要
睡眠によって勉強の効率化を目指すためには、質の良い睡眠を確保することが欠かせません。
例えば睡眠中に電話の着信音で起こされないようスマホの電源を切っておいたり、リラックスして眠れるように部屋の環境を整えたりと、睡眠時間も無駄にしないための対策も大切です。
勉強時間は1週間で少なくとも20時間を確保
ライフスタイルに勉強時間を取り入れる
事前の知識や経験など個人差も大きいものの、一般的に、二級建築士の合格までに必要な時間はおよそ1000時間と言われています。
仮に1年間で二級建築士の合格を目指す場合、1ヶ月に80時間前後、1週間でおよそ20時間を勉強にあてる計算です。
普段の生活を続けながら1週間で20時間の勉強時間を確保する場合、例えば以下のような割り当ても考えられるでしょう。
- 平日(月~金)に2時間ずつ:合計10時間
- 土日に5時間ずつ:合計10時間
もちろん、生活スタイルによって土日祝日の勉強時間を増やしたり、平日の勉強時間を少なくしたりといった調整は必要ですが、基本的には勉強そのものを習慣化できるよう、ペースを一定に保ち続けることも大切なポイントです。
なお、ゴールデンウィークのような連休期間中は、普段とは違った時間配分で集中的に勉強するといった方法もとれます。
具体的なスケジューリングで目標を明確化
試験日程をベースにスケジューリング
建築士の試験で合格を目指すには、最初に目標を明確した上で、それに合わせてしっかりと勉強スケジュールを構築しなければなりません。
効率的な勉強は、目的に沿って成果を確かめながら続けることで、効率性を高められ、また本人の自信にもつながります。事前のスケジュールと自分の現状の成績を比較することで、どのポイントを予習・復習すべきか再確認できることもあるでしょう。
建築士の学科試験は例年、7月の第4日曜日に実施される予定となっており、スケジュールを考える場合はその試験日をゴールとして逆算することが基本です。ただし、さまざまな要因による日程変更など、必ずしも試験日が毎年同じとは限らないため、適切に情報確認をする意識も大切です。
仮に夏から勉強をスタートさせるとして、具体的には以下のようなスケジューリングが一例として想定されます。
- 8月~10月:自分に合わせた勉強スタイルを考えて全体のスケジュールを立てる。
- 11月~1月:スケジュールに沿って勉強を続けながら年末年始には集中的な勉強時間を確保する。
- 2月~4月:年始の内容を復習しながら過去問を解いて実践形式の勉強をする。4月の模試も活用して進捗を把握する。
- 5月~6月:連休を利用しながら模試で判明した弱点を集中的にカバーしつつ、過去問を繰り返して試験のペースを身につける。
- 7月~試験直前:全体のミスや弱点を再確認しながら、ケアレスミスによる点の取りこぼしを減らす。また体調管理とメンタル管理を徹底して試験に備える。
もちろん、勉強をスタートさせる時期やライフスタイルによって違いは色々と生じますが、試験の実施日は全国一律となっているため、あくまでもゴールを起点としたスケジューリングが重要です。
季節ごとのイベントや注意事項もある
その他、季節性インフルエンザや花粉症など、季節や体質によって体調不良のリスクが高まることもあり、自分の体調やペースを考えながら余裕あるスケジューリングを考えるようにしてください。
テキストは種類よりも活用法が重要
自分にとって使いやすいテキストを選ぶ
テキストは極端に安かったり明らかに古かったりしなければ、基本的にどのような出版社や団体が提供しているテキストでも自由に選んで問題ありません。むしろ、出版社や値段を考えるよりも、テキストの中身を読んで理解しやすいか、必要な情報を確認しやすいかなど、自分のスタイルや理解度に合わせて選ぶことがポイントです。
その上で、テキストの量や種類を買いそろえるのでなく、自分の持っているテキストの内容について理解度を深めていく意識を持つようにしましょう。
例えば、自分が間違いやすい部分や絶対に覚えておくべき部分については、マーカーで線を引いたり、付箋を貼ってすぐに情報へアプローチできるようにしたりといった工夫も大切です。
自分なりの勉強法やルールを作る
マーカーや付箋の色を合わせておくことで、赤色のチェックは間違いやすいポイント、黄色のチェックは絶対に覚えておくべきポイント、といったように自分自身の理解度を高めるられます。
テキストに書かれている法令は、出版社や書籍によって異なるものでありません。もしもテキストの内容を理解できなかったり、どのテキストを使っても成績が上がらなかったりといった場合、テキストの種類が悪いのでなく、勉強の仕方を冷静に見つめ直すことも必要です。
法規の勉強は例年の出題傾向を把握する
情報へアプローチする速度を育てる
法規の勉強は、テキストで基礎を固められたら、なるべく早い段階から法令集と過去問を使った勉強をスタートさせ、知識だけでなく情報へアプローチする速度を身につけておくことが大切です。
法規の問題は一定の出題傾向があるとされており、過去問を繰り返すことで、どのような問題が使用されやすいのか傾向と対策を実践形式で学ぶこともできます。
法規を丸暗記すべきかどうかは人による
法規の試験で重要なポイントは、いかに早く正確に法令集と問題内容を結びつけられるかということになります。そのため、考え方によっては法規の丸暗記は必要ないといえるでしょう。
すでに法規に関する知識があれば、暗記した上で理解することも良いですが、法規の暗記だけに勉強時間を費やすよりは、ひとまず試験の解き方を習得することが先決です。
模試や過去問で現在の実力を客観的にチェック
予行練習としての過去問の活用
実際の試験で使用された過去問を使うことで、毎年の出題傾向を把握できるだけでなく、試験の予行演習として時間配分なども確認することができます。
建築士の試験合格で注意すべきは、全ての問題を解くことでなく、解ける問題を確実に解くことです。そのため、過去問を使って実践スタイルの勉強を定期的に実施することも大切なポイントの1つとなります。
模試を使って客観的に実力を評価
模試は単に問題を解く練習としてだけでなく、現在の自分の理解度がどのくらいか客観的に評価することができます。
結果が悪ければ勉強法を見直して復習を強化し、結果が良ければそのまま自信を持って勉強を続けられるでしょう。
結果の善し悪しに関係なく、過度にショックを受けたり、油断したりしないように注意することが肝要です。
合格するために必要なもの
建築士の資格を取るためにはいくつか必要なものがあります。
それはスタートラインに立ち、合格までの長い道のりを歩いて行くためのものとも言えるでしょう。
受験資格
まず、建築士になるためには建築士の受験資格を満たしていなくてはなりません。二級建築士の受験資格としては以下のようなものがあります。
- 大学・短大・専門学校の建築学科の卒業者(実務経験不要)
- 大学・短大・専門学校の土木科を卒業し、かつ1年以上の実務経験がある
- 7年以上の実務経験がある
- 高校の建築・土木科を卒業し、かつ3年以上の実務経験がある
一級建築士の受験資格は次のようになっています。
- 二級建築士としての4年以上の実務経験
- 大学・短大・専門学校の建築学科・土木科を卒業し、一定の実務経験を積んでいる(4年制大学卒は2年以上、3年制短大卒は3年以上、2年制短大卒と2年制専門学校は4年以上)
建築士の資格試験を受験するためにはこのような要件を満たす必要があるのです。
大学入学後の場合は、専門学校に行くか7年以上の実務経験を積まなくてはなりません。その上で二級建築士を取得し、一級建築士へとステップアップしていくルートになるでしょう。
時間
受験資格を満たしたら、次は何といっても時間が必要です。
初学者の方なら、一級建築士は2,000時間以上、二級建築士でも1,000時間以上の勉強時間を確保したほうが良いと言われています。
この勉強時間の確保が、建築士取得にとって最初の課題と言えそうです。
毎日ある程度まとまった勉強時間が取れる方であればいいのですが、そうではない方も多くいらっしゃいます。仕事をしていたり、学校に行ったりしている場合は尚更でしょう。
その際は、通勤時間やちょっとした時間のような細切れをうまく使っていく工夫が重要です。
また、睡眠時間は極力確保しましょう。睡眠時間を削って勉強することもあるかと思いますが、それはあくまでイレギュラーです。資格取得までは長丁場ですので、くれぐれも無理は禁物です。
モチベーション
勉強時間の確保ができたら、いよいよ勉強の開始です。
ただ、勉強時間を確保したとしても、モチベーションが保てなければ合格はできません。このモチベーションが保てなかったために、途中で脱落してしまう方もいます。それだけモチベーションの維持というのは難しいものであり、維持するためには工夫が必要です。
たとえば、自宅以外で勉強するのも良いでしょう。環境を変えれば、意外と勉強が進むということもあるかもしれません。
しかし、一番大切なのは「モチベーションを保つのは難しい」と理解しておくことです。「モチベーションを保つのが困難」と理解していれば、それに対する工夫もできます。
また、どうしてもモチベーションが上がらない場合、1日5分でもいいからテキストを開くことも大切です。
時間は短いけれど毎日勉強が継続できている。という事実はモチベーションを維持するために大きな力となるでしょう。
アプリ
スキマ時間に勉強する場合、建築士の資格試験対策アプリを活用するのも有効です。
資格試験対策のアプリは多くリリースされており、無料から有料のものまであります。
いくつかダウンロードをしてみて、使いやすいものを選びましょう。その時に、使っているテキストに合ったものを選ぶのも選定のポイントのひとつです。
アプリを活用すればテキストを開く必要がないため、それなりに混雑した電車の中でも勉強が進められます。
疑問に思ったことや理解が不足していると感じた部分を気軽に調べられるというのも、勉強を継続していく秘訣のひとつです。
宅建士と建築士のダブルライセンスのメリット
宅建士と建築士のダブルライセンスを持っていると、不動産取引のスペシャリストとしての証明になるのがメリットです。最近では宅建士を持っている方が、建築士を目指すというケースも多くなっています。
というのも、宅建士の知識に建築士の建築物の設計や工事管理の知識が加われば、周囲からの大きな信頼につながるからです。
宅建士の知識に加えて、建築士の技術的な提案があればより大きなプロジェクトでの活躍が期待できます。
大型商業施設の設計であれば、建築物そのものから融資先・出店店舗との賃貸契約までワンストップで計画を進めていくことが可能です。これは自身の仕事の幅を広げるのと同時に、クライアント側から考えても頼りになるでしょう。
また、試験科目の面においても、建築士と宅建士は重複しているものが多くなっています。宅建業法における宅地建物取引業法や建築基準法などです。そういった意味でも相性が良く、ダブルライセンスを取得するメリットは大きいと言えます。
海外で活躍したいなら持っておいたほうが良い資格
建築士を目指す方の中には、海外で活躍したいという方もいるはず。その場合、持っておいた方が良い資格があります。
施工管理系の資格
図面読解や計画を立てるときなど、知識や技術を培っておくことで品質を確保するのに役立ちます。
認定コンストラクション・マネジャー
日本コンストラクション・マネジメント協会が実施している試験で取得できる資格です。プロジェクトを全体的に調整して、目的達成のために動きやすくするための力を培えます。
語学系
働きたい場所で使用する言語は、最低限覚えておく必要があります。資格を取得する必要はありませんが、伝えたいことを齟齬なく伝えるためにも勉強は必須となるでしょう。
諸外国によって建築家試験制度は異なる
オーストラリアでは小論文と面接、アメリカではコンピュータによる多枝選択式と製図など、国ごとに試験方法が異なります。それぞれの国の試験内容や受験資格を確認することで、何が重視されるのかも知っておくのも良いかもしれません。
まとめ
お伝えしたように独学で建築士になる方法はあります。
もし独学で建築士の資格取得に不安を覚えた方には、通信工場や専門学校に通うという手段もおすすめです。
特に専門学校の場合は費用はかかるものの、ゼロから建築士を目指せます。その場合でも、あなたに合った建築系専門学校を選ぶことは重要です。自分に合った方法を選び、建築士の資格取得を実現していきましょう。