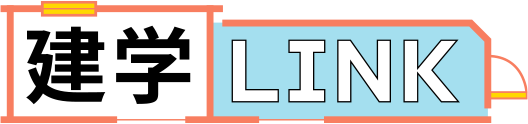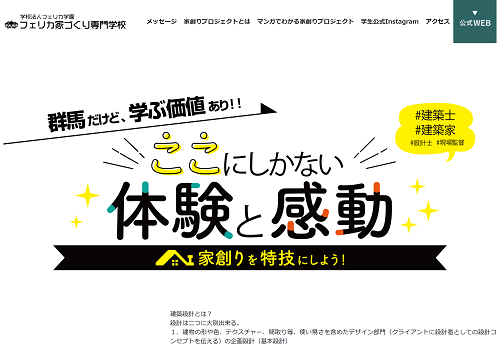建築設備について
このページでは建築士になるにあたって、基本であり必要な知識でもある建築設備の意味や特徴、建築基準法の対象かどうかについて分かりやすくまとめました。建築士を目指している方は、参考にしてみてください。
建築設備とは
建築設備は、一見すると建築物に付属しているようなイメージですが、人に例えると内臓器官や血管など重要な要素です。具体的には、給水設備や空調設備、電気設備などが建築設備に該当しています。
なお、室内だけでなく建築物の外に設置している設備も建築設備です。
私達の生活は建築設備に支えられていて、どれか1つでも止まってしまうと日常生活の難しい状況になってしまいます。マンションの電気設備が故障してしまうと、室内の照明やコンセントをはじめ、非常用発電機なども稼働できません。
建築士を目指す方は、建築設備の基礎知識も覚えるのが大切です。
それでは、各建築設備の定義や特徴などについて紹介していきます。
給排水設備
建築設備において給排水設備とは、給水管や排水管、ポンプ設備、受水槽や高置水槽などさまざまな水回り設備のことを指します。また、給排水設備は、給水設備と排水設備の総称で、それぞれ水の供給と排水を行う設備です。
給水設備は、外部の水道管から流れてきた水を建物内部に供給する設備を指していて、給水管や給水ポンプ・タンク、給湯設備などが担っています。
給水管は、水道水を運ぶパイプで、給水ポンプで1階から上昇階へ水を組み上げます。そして、給水タンク(高置水槽)に貯めておきます。
一方排水設備は、キッチンやトイレ、浴室などで使用された水を下水道へ流す設備を指していて、下水を流す排水管や下水道本管へ流す排水ポンプ設備などで構成されています。
空調設備
建築設備における空調設備とは、空気調和設備のことで温度に加えて空気の流れ(気流)をコントロールできたり空気清浄機能が付いていたりしている設備を指します。また、5つの機能に分けることができ、換気、温度調整、加湿器、除湿器、配管(ダクト、空気を流す配管)いずれか1つの機能を持った設備を空調設備と呼ぶことができます。
なお、一般的な家庭用エアコンは、冷暖房設備とも呼ばれていて空調設備の5機能を持っています。
空調設備は、人が快適に暮らす上で重要な役割を担っています。たとえば、配管が故障してしまうと、冷たい・暖かい風が流れませんし、湿度のコントロールができないと快適に過ごすこともできません。
電気設備
建築設備における電気設備は、キャビネット、受変電設備、建物内部に電気を供給するための幹線ケーブルなどを指しています。また、マンションでは、非常用発電設備も設置されています。
キャビネットは、電力会社側の配線と建物側の配線を接続している設備をカバーする収納機器です。受変電設備は、変電所から送電された電気の電圧を調整したり配電したりするための設備で、基本的に建物内部に設置されています。
建物内部に配電された電気は、分電盤を通して各部屋や照明設備などに供給される仕組みです。
建物によっては蓄電池や太陽光発電設備も設置しており、それら設備と接続する場合もあります。
建築設備は建築基準法の対象
空調設備や電気設備、給排水設備は建築設備に該当し、建築基準法の対象となります。ただ、建築基準法の確認申請に関しては、昇降設備など一部の設備に限られています。
まとめ
建築設備は、私達の生活を支える電気・水・空気に関する設備を指しています。また、建築設備は、建築基準法の対象となるので、建築基準法に沿って設計および配置、運用する必要があります。
これから建築士を目指す方は、建築物の構造やデザインだけでなく、空調設備や電気設備、給排水設備などの建築設備の構造や仕組み、各種機器類の概要についても理解するのが大切です。
定期報告制度の施行
定期報告とは、建築基準法により定められた報告制度です。建築基準法の第8条に「建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。」と定められているように、建築基準法で、建物を所有・管理している人は、例外なく、適切な維持管理義務があることが明記されています。
さらにその上、第12条に「資格を有する者にその状況の調査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。」とあります。平成20年と平成28年に大きな法改正を行っていて、制度の内容、調査・検査の内容もより厳格になり、対象となる建築物も拡大されました。平成28年の法改正では、国が政令で最低限の対象建築物の用途や規模を指定するようになり、これは、火災事故等など発生時において、高齢者など、避難困難者の人を優先しています。
その他、都道府県や市町村によって、報告年度や報告内容などに違いがあります。
参照元:定期報告.info 定期報告とは(https://www.teikihoukoku.info/seidonogaiyou.html)
定期報告の内容
定期報告は、建物を安全に維持保全するのが目的。実際に建物が建設されて利用されるまでには、「企画・設計、【確認申請】、【中間検査】、【完了検査】、利用開始」という流れがあり、適法に検査を受けていれば安全性は確保されていることになりますが、この後の安全性の確保は、所有者や管理者に委ねられるのが当たり前です。
そのため、事故などが起こらないように、建物が適法に保たれているか、建物の維持管理がきちんとできているかをチェックするというのが、定期報告制度なのです。定期報告には、特定建築物、建築設備、防火設備、昇降機等があります。多くの建物で対象となるのが、特定建築物、建築設備、と、新設された防火設備の3種類です。
定期報告の調査内容については、6項目に分けられます。
- 敷地及び地盤
- 建築物の外部
- 屋上及び屋根
- 建築物の内部
- 避難施設等
- その他(免震装置、避雷設備など)
です。この6項目の中にさらに細かく調査項目があり、劣化状況や防火区画などの法的な問題などをチェック。そして、その内容を報告書にまとめて特定行政庁へ報告します。平成20年の法改正に伴って調査項目が追加され、是正箇所の写真添付が必要になりました。
参照元:定期報告.info 定期報告とは(https://www.teikihoukoku.info/seidonogaiyou.html)
定期報告の対象
今までは、地域の実情に応じて特定行政庁(建築主事を置く地方公共団体)が報告の対象を定めていました。
平成28年6月1日の改正により、避難上の安全確保などの観点から、「不特定多数の者が利用する建築物及びこれらの建築物に設けられた防火設備」「高齢者等の自力避難困難者が就寝用途で利用する施設及びこれらの施設に設けられた防火設備」「エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機」を国が政令で一律に報告の対象としました。
定期検査の内容
建築設備の定期検査では、対象となる建築設備は、機械換気設備、機械排煙設備、非常用照明装置、給水設備及び排水設備(※行政庁により対象外のところも多い)の四つです。目視での状況確認はもちろん、実際に機器を作動させての検査を行います。
機械換気設備では、主にガス機器などがある火気使用室と、外気に面する窓のない無窓の居室の換気量を測定。機械排煙設備の検査では、排煙機本体と各フロアの区画に設置された排煙口での風量を測定します。非常用照明の検査では、点灯確認に加え、避難経路の照度測定も行います。
火災などで電源が失われた場合でも安全に避難ができるよう、最低限の明るさが確保されているかどうかをチェックします。
防火設備の定期検査では、防火扉、防火シャッター、耐火クロススクリーン、ドレンチャー等が対象となります。近年、多くの火災事故が発生していますが、防火設備が適切に機能しなかったために被害が拡大したとして、平成28年6月1日施行の法改正で防火設備の定期検査が新設されました。
目視で、損傷や変形がないかを確認することはもちろん、実際に感知器を作動させ、それと連動して防火設備が作動・閉鎖することを確認することに重点を置いています。