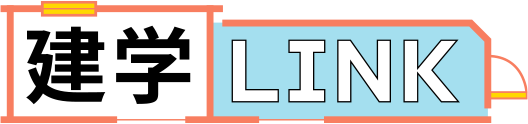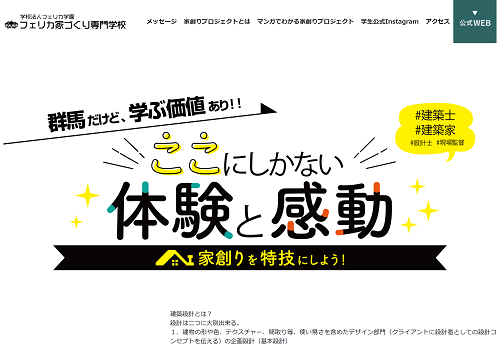建築CAD、CADオペレーターとは
設計・製図できるソフトウェアで図面の作成を行なうCADオペレーター。民間資格である建築CAD検定試験やCAD利用技術者の資格取得が欠かせません。ここでは、CADオペレーターの仕事内容や資格の概要について紹介しています。
CADオペレーターとはどんな仕事か?
CAD(キャド)とは?
CADはコンピュータで設計・製図をするソフトウェアのことです。
建築に特化したものは建築設計CADと呼ばれており、建築関係図を製図する際に用いられています。建築関係図は4種類あり、工事の段階に応じて作成される図面のことです。
建築CADソフトは1種類だけではなく、さまざまな種類があり、それぞれ異なった機能が搭載されています。
CADオペレーターとは?
CADオペレーターとは、CADソフトを用いて図面を作成する方のことです。最近では、機械・構造物から家電製品、洋服のデザインなどあらゆる分野でCADオペレーターが求められています。
建築関係図
- 基本設計図
- 建物の構造や材料、間取りなどの図面。依頼主が希望する使い勝手やデザインを敷地環境・法規制などの条件に当てはまるように検討して作成します。依頼主が理解できるようにわかりやすいものが一般的な基本設計図です。
- 実施図
- 工事に必要な詳細事項を定めるために基本設計図を基に作成した図面。見積もりの作成の時に役立ちます。基本設計図よりも専門的な情報が記載されているので、依頼主が全てを理解するのは難しいでしょう。
- 施工図
- 建築確認申請がおり、実施図を基に作成した図面。この図面を見て施工業者は工事を行ないます。
- 竣工(しゅんこう)図
- 建築工事中の設計変更を修正し、工事が完了してできあがった建物を正確に記した図面。配管や配線などは施工中に変更されることが多いため、竣工図として記録するのです。最新の図面なので、将来修繕やリフォームする際に役立ちます。
建築CADソフトの種類
建築業界でも幅広く利用されているCADソフトであるAutoCAD(オートキャド)。大手企業が使用しているため、下請け業者でも導入されるようになったソフトウェアです。一方中小企業の場合は、フリーCADソフトのJw_cadやDraftSight・設備関係の企業はCADWe’ll Tfasなどのように他のCADを使用しています。
AutoCAD
汎用性の高いCAD
AUTODESKが開発委しているソフトウェアで、ゼネコンや建築業に自動車業界など、様々なジャンルにて採用されているCADです。幅広い業界から採用されているのは、それだけ汎用性が高いからこそでしょう。
比較的初心者であっても操作しやすい一方、自由度が高い点もポイントです。無償体験も用意されているので、期間限定で利用できます。ツールも充実しており、2Dと3D両方の作業を行えるのもメリットです。パソコンはもちろん、スマホやタブレットでも利用できます。
Jw_cad
2次元用のフリーソフトウェア
Jw_cadは2次元の図面を作成できるCADです。最大の特徴は、フリーソフトウェアであること。CADソフトは高額なものもありますので、導入したいとは思っても予算の面で断念せざるを得ないものもあるかもしれません。一方、Jw_cadはフリーソフトなのでダウンロード環境さえあれば誰もが自由に使用できます。
建築士が開発に協力していることもあり、建築士のニーズに応えた出来栄えとなっているのも魅力の1つです。フリーソフトながら、使い勝手の良さが好評を集めています。
DraftSight
AutoCADとの連携が可能
DraftSightもまた、2次元図面を作成するためのCADです。Jw_cadと同じくフリーソフトなので、ダウンロード環境さえあれば誰もが自由に使えます。加えて、AutoCADのコマンドをそのまま使用できる点も特徴です。AutoCADに使い慣れていた人であれば、感覚的に活用できるでしょう。フリーソフトではありますが、ソフトウェア会社であるダッソー・システムズ社が開発しているので信頼性も問題ありません。
CADWe’ll Tfas
建築設備特化型
CADWe’ll Tfasは、図面よりも建築設備に強いことで知られています。電気や空調、衛生などの設備専用機能が用意されており、設備は3Dでの表示も可能です。機能の特性上、図面よりも建築設備の設計等で重宝されています。株式会社ダイテックが開発しており、開発元がしっかりとした企業である点から信頼できるCADだと言えるでしょう。
VectorWorks
プレゼンに強いCAD
Nemetschek Vectorworksが開発するVectorWorks。特徴は2次元製図だけではなく、3次元のモデリングも可能と汎用性の高さがあることです。スケッチ、意匠図からのCGパースが可能、線や色の選択肢が多いのもメリットとして挙げられます。カラフルな図面の作成ができるので、プレゼンのように人に見てもらうための図面作成にも定評のあるソフトです。体験版が用意されているので、インターネット環境さえあればお試しで使用できます。
DRA-CAD
建築法規のチェックも可能
株式会社建築ピボットが開発を行っているDRA-CAD。2次元製図と3D機能が備わっている建築CADとして、実用性の高さが特徴です。他のCADでは見られない木造壁量計算や日陰、天空率といった建築法規までチェックできるので、より専門的な製図を作成できます。その分、使いこなすためにはスキル・知識が求められるのが気になる点です。ただ、インターフェイスそのものは決して複雑ではありませんので、他のCADを使ったことがある人であれば感覚的に使用できるでしょう。
BIM
画面で部材の組み立てが可能
Building Information Modelingから「BIM」と名付けられています。3次元のモデリングに強い点が特徴で、特に最大のポイントは画面上で部材の組み立てが行える点です。実際に組み立てる前に、それまでは組み立てなければ分からなかったことが分かるようになりました。
また、すべてのデータに連動している点も特徴です。1カ所修正することで、必要な部分を自動的に修正してくれるためかける時間の短縮も狙えます。
Revit
複数同時進行が可能なCAD
建築や施工などの業種のために開発されたRevit。建物のモデリングだけではなく、システムや構造の解析にシミュレーションができます。複数の人間で同時に編集が行えるので、同時進行の作業を行えるのがメリットです。
また、仕上げ用や健具表といった図面の作成も可能なので、高い汎用性を持ちます。図面ソフトウェアを開発しているAUTODESK社による開発なので、安心感もあるでしょう。
ARCHICAD
申請サポートもあるCAD
GRAPHISOFT(CADソフトウェアメーカー)が開発したとあって、ビジュアル面に力が入っているARCHICAD。CADではあるものの、直感的な操作が可能なシンプルなインターフェイスが特徴です。
また、設計だけではなく申請までサポートしている点や共同作業できる点も特徴として挙げられます。建築や建設業界に活用されていることが多いのも、業界のニーズを的確に捉えているからこそ。実用性に長けているシステムが好評を博しているCADです。
建築CAD検定試験、CAD利用技術者の資格概要
CADの資格には公的資格と民間資格の2種類があります。公的資格である厚生労働省の中央職業能力開発協会の「CADトレース技能審査」は、国内の公的資格として認められている資格です。民間資格は多くのCADの資格があります。
主に、全国建築CAD連盟の「建築CAD検定試験」や、コンピューターソフトウェア協会の「CAD利用技術者試験」の資格が主流です。国内での認知度が高いため、多くの方が受験しています。実践的な資格として企業からも評価されている資格の一つです。
建築CAD検定試験の概要
一般社団法人全国建築CAD連盟が主催する建築CAD検定試験。1993年に誕生した建築CADの資格試験となります。建築CADを用いて図面を作成する技能を測ったり、CADシステムを使って建築図面を正しくトレースする技能を測ったりする試験です。
実技試験のみの試験ですが、基礎的な建築知識が必要となります。合格すれば、建築CADの実用性があると高く評価してもらえるでしょう。准1級から4級までのランクがあります。
主催団体について
建築CAD検定試験を主宰しているのは、一般社団法人全国建築CAD連盟です。AACLとも略されているこの連盟は、国家試験ではないものの全国で様々な職業訓練校、建築系の大学や専門学校、さらには工業高校等でも実施されています。建設業の需要が高まることでCADへの注目度も高まっているのが現状です。
資格を取得することで、ある程度CADを使いこなせる点が証明できます。学生や異業種からの転職であれば、資格を持って建設業界の門を叩くことができるのがメリットです。既に建設業界に身を置いている方であれば、資格取得でキャリアアップも狙えるでしょう。
受験方法について
一般受験と団体受験の2つの受験方法が用意されている点も、建築CAD検定試験の特徴です。個人での受験が一般受験として受けられます。一般受験の開催頻度は、年に2回です。
一方、通学している学校が団体登録している場合、学生は団体受験となります。団体受験の場合、試験は学校が会場です。全国の「試験認定校」であれば、年に4回、さらには1名からでも受験を受けられます。この点からも分かるように、試験認定校の学生であれば、CAD試験は「チャンスの多い資格」であることが分かるのではないでしょうか。これから試験認定校への試験・入学を控えている方は、CAD試験についても確認しておくのもおすすめです。
CAD利用技術者試験の概要
一般社団法人コンピュータソフトウェア協会が主催するCAD利用技術者試験。CADシステムに関する知識の理解することが大切で、建築図面、機械図面などさまざまなトレース技術が求められます。パソコンに関する知識やソフトウェアに関する知識について試験問題として出題されることも。
建築CAD検定試験と違って学科を行ない、CADを利用する仕事で勤めている方や、就職・転職を考えている方の多くが、資格の試験を受けているそうです。
試験にて使用されるCAD
建築CAD検定試験で使われるCADは汎用性が高く、かつ図面の自動生成機能を持たないCADを使っての受験となります。ちなみに、どのCADが用いられるかは各々の自由ではありますが、各級で使われているのはJw_cadです。
次いで多く使われているのがAutoCADです。ただし、割合にするとJw_CADが各級において5割から9割となっているので、ソフトの操作感には慣れておいた方が良いでしょう。
建築CAD検定試験の勉強方法
試験に合格するためにはもちろん勉強しなければいけませんが、勉強方法を大きく分類すれば独学が通学かになります。独学の場合、建築CAD検定試験問題集、あるいは建築CAD検定試験公式ガイドブックなどが良いでしょう。建築CAD検定試験問題集は、試験を主宰している一般社団法人全国建築CAD連盟が発行しています。過去1年間の問題が掲載されており、かつ主催団体が発行しているので信頼性が高いです。
公式ガイドブックに関しては主催団体ではないものの、全国建築CAD連盟の顧問による著書なので、こちらも信頼できるでしょう。独学の場合、自分のペースで勉強できる点は大きなメリットですが、一方では自分との戦いになります。スクールであれば試験までしっかりとサポートしてもらえる一方で、時間や学費がかかるのが気になる点です。勉強については人それぞれ合うものが異なるので、自分に合った方法を見つけることが大切です。
建築CAD検定試験の合格率
全国建築CAD連盟の公式ホームページによると、建築CAD検定試験の合格率は難易度によって変わります。2019年度のデータを見ると4級の合格率は89.8%と高い水準にありますが、
- 3級が71.7%
- 2級が58.6%
- 准1級が24.5%
と徐々に合格率が低くなっているのが特徴です。
受験申込者に関しては、増加傾向にあります。この点を見ても、建設業界への注目度が高まっている点が伺えるでしょう。注意点として、合格率はあくまでも絶対的なものです。合格点を上回ることで合格となりますので、合格者がいないケースもあります。実際、2014年度の准1級試験の合格率は0.0%、つまりは0人でした。
級の目安
建築CAD検定試験には准1級から4級まで用意されています。准1級が一番難易度が高く、合格率は低めです。
大まかな目安として、4級はCADトレースの一般的な業務が行えるレベルです。いわば基礎ではありますが、今後経験を積むことでよりスキルアップを目指すための試験だと考えて良いでしょう。
3級に関しては、実務で建築図面を描けるレベルとされています。基本的な操作も求められるのが特徴です。試験問題も、「指示に対してどれだけ正確にこなせるのか」が問われます。CADの操作スキルはもちろんですが、どれだけ正確に要求を把握できるのかも合格するために重要なポイントです。
2級に関しては、一般建築図をCADを使って作図が可能なレベルが求められます。CADの操作スキルは当然ですが、建築や設計に関する基礎知識に立面図の作成、図面から建物を立体的に捉える力が必須です。実用性の高いランクとなるので、2級を取得しておくことで建設業界へのチャレンジが可能になったり、あるいはスキルアップもできます。2級取得者は、いわば「即戦力」だと考えて良いレベルにあるので、転職においても有利になるでしょう。
准1級は「CADが使える」というレベルを超え、卓越した能力を持っていると考えられます。建設業界への就職や転職に関しても、即戦力クラスとして歓迎されるでしょう。難易度の高さを踏まえると、建設業界であればどの業者であっても喉から手が出るほど欲しい存在だと言えます。
合格のポイント
様々な級の試験が用意されている建築CAD検定試験。合格のためのポイントとしては、「問題をしっかりと読み理解する」に限ります。どれだけスキルがあるとしても、問題を正しく把握しなければ、答えも間違ったものになってしまうでしょう。正しい答えを導くためには、まずは問題を正しく把握することが大切です。そのうえで、それぞれの級のポイントを抑えておきましょう。
4級のポイント
4級の試験に関しては、設計者から指示さえあればCADを駆使して設計図をかけるレベルとされています。4級に関しては89.8
%(2019年度)という合格率を見ても分かるように、決して難問ではありません。CADの基本的な操作を理解していれば合格のチャンスは十分にあるので、勉強をしておけば問題ないでしょう。
※4級は高校での団体受験のみを受け付けています
3級のポイント
3級も4級と同じく、指示に対して正しく製図できるのかが問われます。こちらも合格率が71.7%(2019年度)と高いのがポイントです。3級と比べると多少は難しいものの、まずは冷静に問題を把握するよう努めましょう。
2級のポイント
2級になると、難易度が高まります。参考図が実務レベルの設計者によるラフスケッチにで、そこから図面を制作しなければいけません。問題を理解するのはもちろん、ラフスケッチの意図まで正しく把握する必要があります。
具体的な図面の書き方や完成させるためのパターン、CAD操作などを覚えておくのがおすすめです。
准1級のポイント
准1級で求められるものの1つは正確性です。4~2級は7割以上の得点で合格でした。しかし、准1級に関しては公式にアナウンスされていません。トレース試験はありますが、3級や4級とは「別物」となっている点は覚悟しておきましょう。試験時間は4時間10分と長く、その分内容も細かいものとなっています。
合格に近づくためにも、CADの操作やバリアフリー新法で規定されているサイズの把握をしておきましょう。作図を効率的にできるよう操作に慣れておくことも、重要なポイントです。
CADオペレーターと設計者との違いについて
CADオペレーターと設計者は、似ているようで異なる存在です。設計者はアイディアや独創性を求められます。0から生み出すことになりますし、当然そこには現実的な視点を踏まえたうえでの設計力が不可欠です。
一方、CADオペレーターに求められるのは独創性ではなく、設計者の独創性を形にする「正確性」です。設計者の意図を正しく把握した図面の制作が求められるため、独創性や自由さではなく「正しい製図能力」が求められます。
CADオペレーターに向いている人
几帳面で正確さを持っている人
CADオペレーターには、設計者のアイディアを形にする正確性が必要です。何かを生み出すことよりも、指示に対して忠実に、正確な仕事をこなせる人の方がCADオペレーターに向いています。自分自身の仕事にミスがないかを確認する几帳面さなど、「ミスをしない」という責任感も大切です。
集中力や忍耐力
CADオペレーターのお仕事は、長時間一人でパソコンと向き合って地道にコツコツとこなします。人とわいわいではなく、一人で画面と向き合いながらコツコツと作業をこなす。納期に間に合うよう作業配分もしなければならないため、時間や体調の管理も必要です。
向上心
ただ単に作業をこなすだけではなく、向上心も大切なポイントの1つです。何ができるのか、自分の設計した図面がどのような形で役に立つのか。図面設計を繰り返すことで自分自身のスキルが高まっていることを実感し、喜びに繋げられる人もCADオペレーターに向いています。
CADオペレーターの将来性
今後、CADソフトが開発されて使いやすくなり、誰でも扱えるようになるため、CADオペレーターとしての資格や技術を持っているだけでは安心できません。現段階のソフトの技術力アップによって、専門のCADオペレーターを雇わずに設計士がCADを使って図面を作成するケースが増えています。CADの操作知識や技術はもちろん必要ですが、将来のことを考えて建築に関係のある業務知識も身につけておきましょう。
これからはCADオペレーターも専門知識が必要です。現場で作業する際には土木建築の知識を求められており、CADオペレーターに対して求められるレベルは徐々に上がっています。
CADオペレーターになるには、簡単ではありませんが、コツコツと磨き上げた技術と経験を自分の強みとして活かすことが可能です。建築関係の深い知識を持つCADオペレーターになれれば、建築関係の企業で重宝される存在となれるでしょう。自分の努力次第でレベルアップしていけば、良い条件の会社に勤めたり難しい仕事を任せてもらえたりするので、やりがいを感じる仕事だと言えます。CADオペレーターとして活躍したい場合は、CADが操作できるだけではなく、業界の専門知識を身につけることが大切です。
CADオペレーターになるには、建築CAD検定試験、CAD利用技術者の資格をはじめとした建築関連の資格取得が欠かせません。さらに建築関係の資格の取得も将来役に立ちます。ここでは、資格取得をサポートしてくれる建築専門学校についてまとめたので、こちらをチェックしてみてください。