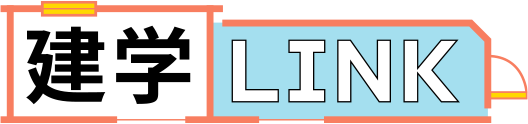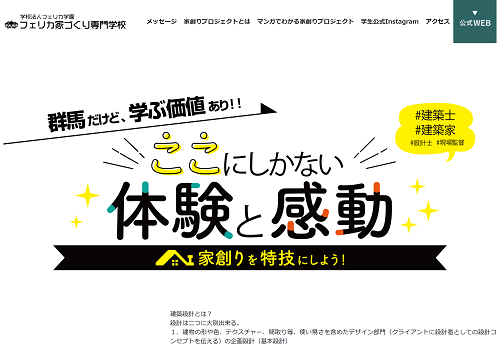建築施工管理技士とは
建設・建築工事の現場監督を行なう建築施工管理技士。6つに分かれている施工管理技士の職域区分の一つです。ここでは、建築施工管理技士の業務内容や必要な資格についてまとめています。建築施工管理技士に興味がある方は、ぜひ参考にしてください。
建築施工管理技士とはどんな仕事か?
施工管理とは何か?
施工管理は、土木・建設・建築・電気工事などの現場で、職人や職工の作業工程の進捗を管理し、安全かつ規則が守られているのかをチェックすることです。施工計画の作成や資材の調達などの業務もあります。建築施工管理技士が行なっている業務には、以下の「施工管理の4管理」というものが重要です。
施工管理の4管理
- 原価管理
- 人件費や材料費の原価を計算して、作業工程が赤字にならないように管理することです。
- 工程管理
- 工期を守るために工事の日程や作業員の数、材料の到着予定を調整します。
- 品質管理
- 質の高い建造物を建築するために、構造物の強度や精度が基準値を満たしているのかをチェック。
- 安全管理
- 工事現場での事故が起こらないように設備を整え、安全に関する情報を共有して注意喚起を行なう管理のことです。
施工管理技士の資格は6つに分かれており、それぞれ対応できる業務が異なります。1級と2級では責任の重さや対象業務の広さなどに違いがあるのです。施工管理技士の6つの区分について紹介します。
施工管理技士の6つの区分
- 土木施工管理技士
- 河川や道路、橋梁などの大規模土木工事の施工管理を行ないます。
- 建築施工管理技士
- 鉄筋工事や大工工事、内装仕上げ工事などの施工管理を行ないます。
- 管工事施工管理技士
- 冷暖房設備や空調設備、給排水・給湯設備など管工事の施工管理を行ないます。
- 電気工事施工管理技士
- 電気工事に関する施工管理を行ないます。
- 造園施工管理技士
- 公園や緑地、遊園地などの造園工事の施工管理を行ないます。
- 建設機械施工技士
- 建設現場で建設機械を用いた施工を行なう際の指導・監督業務を行ないます。
施工管理職の業務内容
施工計画を立案して現場で工事の進行の指揮を行う施工管理職。6つの区分の一つである建築施工管理技士は、建築の分野に分類される施工管理職です。住宅やマンション、ビルや工場などを建設する建築の分野や、ダムや道路、河川の改修などの社会基盤に関わる大がかりな土木の分野に分かれています。
建築業界からみた施工管理職
建築業界では、2010年頃まで積極的に施工管理職の採用を行なってきませんでした。しかし、現在は団塊世代の社員が退職を迎えており、施工管理職の人手不足が深刻になっています。特に20代後半~30代前半の若手技術者が不足気味です。
建築施工管理技士の種類
1級建築施工管理技士
1級建築施工管理技士は、建設工事の規模・ジャンルを問わずに施工管理が可能です。建設工事は16種類に分類することができますが、これらの工事全てにおいて施工管理が行われます。その点では、1級建築施工管理技士は取得しておいて間違いのない資格でしょう。近年労働者不足に悩まされている建設業界にとって、1級建築施工管理技士取得者は喉から手が出るほど欲しい存在です。
2級建築施工管理技士
2級建築施工管理技士は1級建築施工管理技士と比べて、施工管理を行える公示が少なくなります。さらに2級建築施工管理技士の場合、建築、躯体、仕上げの3種類に分かれているのが特徴です。それぞれ管理できる工事が異なるため、1級建築施工管理技士と比べると「すべてにおいて自由」とは言えません。現実的に2級建築施工管理技士は小規模な工事管理を行うケースが多くあります。
働く状況によっては1級建築施工管理技士でなくとも良い
大規模な工事は1級建築施工管理技士が必要ですが、会社規模によっては無理に1級を取得する必要はありません。大手デベロッパーともなれば1級建築施工管理技士が必須です。中小あるいは一般住宅を専門にしているデベロッパーであれば、2級建築施工管理技士で十分とするケースも珍しくありません。
一概に「2級建築施工管理技士では不十分」とはならないでしょう。2級のみしか取得していない建築施工管理技士であっても、ステップアップのために1級の取得を目指している人もいれば、特に困っていないとする人もいます。
二級建築施工管理技士の制限について
制限とは?
具体的な「制限」とは、まず2級建築施工管理技士の場合、監理技術者になることはできません。1級建築施工管理技士であれば問題なく行えます。請負代金額が4,000万円以上の建設現場で監理技術者が義務付けられていますが、その際に1級建築施工管理技士を用意しなければなりません。
また、2級建築施工管理技士は建築、躯体、仕上げの3つに分かれているのも制限がかかる理由の一つです。1級級建築施工管理技士の場合、全てを備えているのですが、2級級建築施工管理技士の場合、それぞれ別で管理を行います。それぞれの資格を有するためには3回試験に合格しなければならないのです。
仕事内容について
設計図のチェック
まず基本的なこととして、設計図のチェックがあります。設計図は、いわば工事における取扱説明書です。設計図を見て、どのような工事になるのかは建築施工管理技士であればある程度把握できます。どこでどのような工事が行われるのか細かい部分まで理解できるので、設計図を確認することこそ、建築施工管理技士としての仕事の一歩目です。
工事内容を把握する
設計図・施工図を見てどのような工事になるのかをチェックしたら、完成させるためには何が必要なのかをチェックします。施工方法や人員、設備。これらを把握・確保することもまた、施行管理技士としての腕が問われます。
業者との打ち合わせ
専門業者等との打ち合わせも、施行管理技士の仕事です。施行管理技士は指揮者とも言えます。実際に動いてもらう専門業者に指示・依頼を出すにあたっての打ち合わせがコミュニケーションの役割を果たしているので、円滑な工事のためにはとても大切なポイントです。
安全・工程の管理
工事が始まったら、安全管理と工程管理が施行管理技士の仕事となります。もしも事故が起きてしまった場合、最悪工事そのものを中止せざるを得なくなり、工期が間に合わなくなってしまう可能性も出てくるでしょう。安全管理を徹底すると共に、工期のスケジューリングにも気を配らなければいけません。遅れている部分に対しては、工期に間に合わせるための調整や対策が求められます。
また、工事はいくつかのグループにて行われるので、それらの管理・連携も施行管理技士に求められるお仕事です。
建築士とのコミュニケーション
建築士とのコミュニケーションも、施行管理技士のお仕事で大切な部分です。設計図を作った設計士とのコミュニケーションは、設計図に込められた真意をより理解するためには必要不可欠となります。設計士としても、自分自身の思いを理解してもらうことで、自分自身の理想の建物を立てやすくなるはずです。
1級建築施工管理技士の合格率
1級建築施工管理技士の合格率について
1級建築施工管理技士の合格率は、およそ40%前後を推移しています。下記は実地試験の合格率です。
- 平成27年37.8%
- 平成28年45.6%
- 平成29年33.5%
- 平成30年37.1%
- 令和元年46.5%
合格率が決して高くはない理由として、問題の難しさが挙げられます。なぜ難しいのかといえば、出題範囲の広さです。学科試験では
- 建築学
- 躯体施工
- 仕上げ施工
- 施工管理法
- 法規
これらすべてを勉強しておかなければいけません。実施試験は
- 施工経験記述
- 安全管理
- 躯体施工
- 仕上げ施工
- 施工管理
- 法規
これらも全て勉強しなおかなければ、合格は難しいでしょう。
特に厄介な点が法律です。法律は変更されたり、或いは建設業界に新しい常識ができたりするなどで問題がより複雑化されるケースもあります。平成30年の試験においては、それまで出題されたことがなかった換気、消防設備に関しての問題が出題されたのです。
1級施行管理技士の合格ライン
1級施行管理技士試験の合格ラインは、得点が60%以上と定められています。この数字だけを見ると、決して高いハードルには感じないかもしれません。ただし、幅広く出題される中での60%となので、「広く深く」勉強しなければなりません。学生時代のテストのように、出題範囲にヤマを張って、一つのジャンルだけ高得点を取得すれば…といった手法では対応できない問題も多数あります。広範囲にわたって勉強を行い、様々な知識を持ってテストに向き合うことが重要です。
建築施工管理技士試験の勉強法
参考書での独学
参考書による独学のメリット
参考書での独学の場合、学校に通うよりも安価で、かつ自分の好きな時・好きな場所で勉強が可能です。例えば仕事帰り、自宅では集中力がわかないからと喫茶店あるいは図書館で勉強することもできます。読むだけであれば通勤や通学の電車の中でも可能です。場所問わずに自分のペースで、かつ安価に取り組める点が参考書による独学の大きなメリットです。
動画教材による独学
動画教材のメリット
動画教材はインターネット環境さえあれば、スマートフォンであっても可能な点がメリットです。参考書のように文字だけでは細かいニュアンスが不明瞭で分かりづらくても、動画であればその点も解消されるでしょう。
専門学校に通う
専門学校のメリット
専門学校であれば、合格までエスコートしてもらえる点が最大のメリットです。試験対策の勉強、試験の申込のサポートもしてもらえます。サポートしてもらいながら勉強を進めていくことで、施行管理技士の合格も自ずと見えてくるでしょう。
また、専門学校はいくつもあります。予算やスケジュール、あるいは学校のこれまでの合格者数など実績によって自分が入学したいところを決められるのがメリットです。社会人でも通える夜間も対応している学校もあります。
勉強するためのスケジュールについて
全体的な勉強量の把握
まずは施行管理技士合格のために、勉強する範囲を大まかに把握することが大切です。施行管理技士試験勉強は長期戦となります。決して一朝一夕で何とかなるものではありません。どれだけの勉強量が必要なのか、大まかにで良いので把握しておくと良いでしょう。
そこから試験まで逆算し、勉強する計画を立てます。参考書であれば「1ページ目から頑張ろう」ではなく、合計何ページの参考書なのか、そして試験まで何日までなのかを計算することで、1日当たりどれくらい勉強すれば参考書全てを網羅できるのかが見えてくるはずです。
メリハリを付ける
勉強で大切なことの1つは集中力です。「何時間頑張った」「仕事の後に頑張った」だけではなく、どれだけ新しい知識を吸収できるか、理解を深められるかも重要となります。ダラダラと何時間も勉強するよりも、集中して数十分勉強した方が効率は良いのではないでしょうか。
施工管理技士の試験も同様に、時間ではなくどれだけ身になる勉強をしたのかを考えるようにしましょう。その点では、無理に頑張るよりも休む時は休むというようにメリハリをつけることが大切です。
時には緊張感を持って勉強してみる
試験会場では緊張してしまったがために、自分の実力を発揮できなかったという人もいます。
- 試験時間と同じ時間だけ勉強する
- 定期的に過去問を試験に見立て、試験時間と同じ時間でどれだけできるのかやってみる
など、緊張感を持った勉強をこなすことも大切です。試験中に緊張で覚えた知識を忘れてしまったとならないためにも、覚えるまで復習するようにもしましょう。
建築施工管理技士と建築士の違いについて
建築施工管理技士と建築士は別物です。確かに業務内容が一部重複している点や語呂が似ている点から、何となく同じようなものなのではないかと思ってしまう人がいても不思議ではないでしょう。
それぞれの違いとして、建築施工管理技士はまさに「管理」が仕事です。一方、建築士は「建築・設計」を行います。いずれも大切な仕事である点は間違いなく、両者ともに建設現場では不可欠な存在です。「建築」と「管理」の担当を分け、両者が上手く連携することでより良い建築を行えるでしょう。
2級施工管理技士のメリット
1級施工管理技士よりも取得しやすい
2級施工管理技士の大きなメリットとして、1級施工管理技士よりも比較的簡単に取得できる点にあります。言うまでもなく、1級施工管理技士の資格取得は簡単ではありません。2級施工管理技士も決して簡単ではありませんが、1級施工管理技士と比べれば取得しやすいと言えるでしょう。まずは2級施工管理技士を取得してから、1級施工管理技士を目指すという手法も可能です。
現場によって遜色はない
2級施工管理技士は、現場によっては1級施工管理技士と遜色ない仕事が可能です。例えば費用が4,000万円以下の建設現場であれば、1級施工管理技士と2級施工管理技士の違いはさほどありません。もちろん大規模な現場ともなると、2級施工管理技士ではなく、1級施工管理技士でなければならないことも多々あります。
2級建築施工管理技士は4,000万以下の建設工事が中心になる
2級施工管理技士であればハウスメーカーや工務店など、活躍の場は多々あります。実際にそれらの業者からすると、1級施工管理技士でも2級施工管理技士でも人材として確保したいところもあるはずです
目的を設定しやすい
2級施工管理技士の場合、仕事に対してだけではなくその後の目標を設定できるでしょう。「いずれ1級施工管理技士になる」との思いを胸に、目標に目指して研鑽を積むことで自分ができる幅を広げられます。
もちろん仕事である以上、1級施工管理技士になった後も新しく覚えなければならないことはあるはずです。責任のある仕事を任せてもらえるようになるので、活躍できる場を広げられるという点も2級施工管理技士のメリットでしょう。
ステップアップが見込める
資格を持っていることで昇進しやすくなったり、あるいは報酬が増えたりすることもあります。1級施工管理技士と2級施工管理技士を比較すると、どうしても1級施工管理技士の方がいろいろとできる…と考えてしまうかもしれません。実際には2級施工管理技士で十分という職場もありますし、そのような職場であれば2級施工管理技士を保持していることで昇進・昇給のチャンスもあります。
2級施工管理技士として社内で信用を得たり、新しいチャレンジが可能になったりすることもあるので、取得することで大きなメリットになると考えて良いのではないでしょうか。
1級施工管理技士のメリット
社内での評価が上がる
1級施工管理技士になることで評価され、資格手当を受けることもできるのがメリットです。もし転職をしたいという際も、資格を持っていることで「実力がある」と認めてもらえます。需要は今後もあると考えられるので、施工管理技士として評価を上げたいのであれば取得しておいて損はないでしょう。
監理技術者として働ける
下請けへの請負金額が4,000万以上(建築一式だと6,000万以上)の工事では、1級施工管理技士の設置が必須です。大きな仕事を任せてもらえる分、成功させることで評価も上がります。現場に必ず必要とされる人材なので、どの企業も確保したいと感じているでしょう。施工管理技士は人手不足になっていることもあり、2級建築施工管理技術検定が年1回から年2回に変更されるほど、人材が求められている施工管理技士。若い施人であれば、選べる幅も広いと考えられます。
一級・二級建築施工管理技術検定の資格概要
建築施工管理技士の資格を取得するには、「実務経験」が大事。実務経験は以下の例のような経験が必要となります。
必要な実務経験の例
- 工事管理の経験
- 受注者としての施工管理経験
- 現場監督技術者としての経験
- 建築一式工事(事務所ビル建築工事や共同住宅建築工事など)
- 大工工事(型枠工事や造作工事など)
建築施工管理技士の試験は、「実地試験」と「学科試験」の2つがあり、1年に1回しかありません。実務経験をしながら学科の勉強するのは難しいと言えるでしょう。一方、建築系の専門学校に入学すれば、在学中に二級建築施工管理技士の学科試験を受験することが可能です。そのため、実務経験しながら学科の勉強する必要がありません。
さらに、学歴によって試験資格に必要な実務経験の年数が異なります。大学の指定学科・高度専門士になれる専門学校を卒業していれば、短い実務経験で建築施工管理技士の資格取得が可能です。
建築施工管理技士になるには建築関連の資格取得が必要不可欠です。資格取得サポートが充実している建築専門学校について調べました。取得できる資格や、資格取得サポートの概要についてまとめているので、資格取得を目指す方は、こちらをチェックしてみましょう。